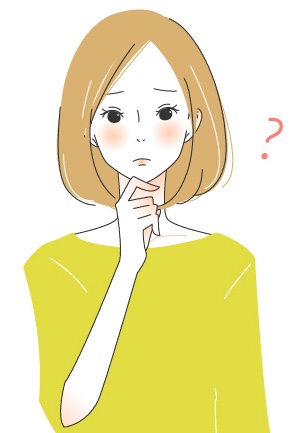
七五三って、誰を呼ぶの?誰と行くの?

両家の祖父母に声をかける人が、多いみたい。
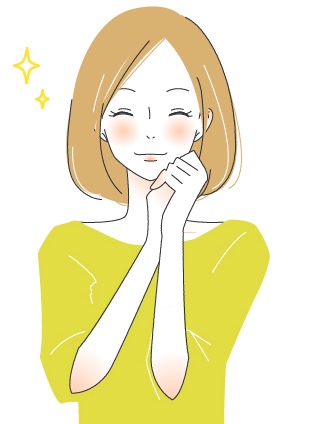
そうなんだ。祖父母が来てくれたら、子どもが喜びそう!
でも、、参加人数が多いと、スケジュール調整も大変そう。食事を誰が用意するのか?誰が払うのか?参拝は、誰と行くのか?そんなことも知りたいなあ。

七五三は、悩むことが多いよね。
こちらの記事を参考に、大変な七五三の準備を少しでもラクにしてね。
お子さんの成長を祈願する晴れやかな七五三。
でも、七五三には、誰を呼ぶのか?誰と行くのか?また、衣装や食事会など誰が用意するのか?誰が払うのか?分からないことがたくさんありませんか?
今回は、七五三にまつわる疑問を解消するべく、七五三の基本のマナーをまとめていきたいと思います!
本音と建前が横行するママのリアルな声にも、少しだけ触れていますので、参考にしてみて下さいね。
七五三は誰を呼ぶ?

お子さんの成長を願うのはパパ・ママだけでなく、祖父母・親戚・友人など多くいると思います。でも、七五三に、どこまで声をかけるべきか?悩みますよね。
ある七五三に関するアンケートによると、全体の60%は、祖父母と一緒に七五三祝いをするそうです。残り40%は、お子さんと両親だけだそう。
そして、声をかけるのは、両家の祖父母が大多数。ただし、遠方で参加が難しかったり、高齢の場合には、無理に呼ぶ必要はなさそうです。
ここで、祖父母に声をかけたママのリアルの声を少し覗いてみましょう。
- どちらも住んでいる場所が近いので声をかけた
- 後から声をかけてくれなかったと言われたくないから、両方の祖父母に声かけをしました
- スケジュール調整が大変なので、日にちを決めてから、都合がよければと両家に声をかけた
- 祖父母は遠方で来られなかったが、もし、来れれば、写真撮影や、子どもの相手など手伝ってもらえたのに
- 同行してくれたことで子どもが喜んでいたし、食事代を出してもらえて助かりました
このように、祖父母の参加に前向きなママがいる一方で、スケジュール調整の難しさや、両家の祖父母で子どもの取り合いになるケース、風習の違いなどで、気を揉むママもいるようです。
せっかくのお祝いなので、祖父母の気持ちを害さないように、うまく配慮したいところですが、ママが疲れない程度に、事を進めていきたいですね。
また、土地柄の風習や、家それぞれの考え方によって親戚一同でお祝いの席を設けたり、家をまわったりするところもあるようです。そんな家柄の方は、七五三の予定を組む前に、祖父母に聞いておくといいでしょう。
祖父母以外にも、叔父や叔母、普段お世話になっているご近所さんや友人などをお誘いするケースもあります。必ず、両親や祖父母など参加者の意見を聞いて、家族で話し合った上でお誘いするようにして下さいね。
次に、七五三の記念写真を残す場合を見ていきましょう!
写真は、後々記念に残るものです。撮った写真にどちらかの祖父母だけしか写っていないとなると、あまりよく思われないようです。写真スタジオには、祖父母も一緒の写真プランなどがありますが、そのあたりも考慮しておきたいです。
最近は、前撮りするケースが増えていますので、お子さんと両親だけの家族写真を撮って、後日、祖父母に見ていただけば、余計な気は遣わずに済むかもしれません。
七五三祝いは、参加人数が多いほどスケジュール調整が難しくなってきます。また、費用もかかります。お参り・記念撮影・食事会のうち、いずれかに限定で参加をお願いしてみるのも良案だと思います。
皆が気持ちよくお祝いするには、事前の相談や報告を、抜かりなくしておきたいところです。
七五三は誰と行く?

七五三当日の参拝は、パパ・ママだけでも、祖父母が付き添っても構いません。最近は、神社の参拝やお祝いの食事会ともに、祖父母に声をかける人が多いようです。
神社の祈祷に両家の祖父母が参加する場合、予約の際に、参加許容人数を確認しておくといいでしょう。人数制限があるような場合には、祖父母には、食事会からお越しいただくという選択肢もあります。
また、長丁場になる七五三なので、ついお子さんの体調ばかりに気が行きがちですが、高齢の祖父母の体調にも気を配りたいですね。
祖父母以外にも、叔父や叔母、普段お世話になっているご近所さんや友人などをお誘いするケースもあります。その時は、必ず、祖父母など参加者の意見を聞いて、家族で話し合った上でお誘いするようにして下さいね。
とは言え、食事会の参加人数が増えれば、その分、費用がかかってきます。大切なお子さんのお祝いを盛大にしたいという気持ちはさておき、費用面を考慮してお誘いすることも大切です。
あくまで、主役はお子さんです。多大な負担をかけずにお子さんの成長を祝い、家族の絆が深まるような七五三にしたいですね。
七五三は誰が用意するのか?

衣装・食事会・参拝の予約など、色んな用意をしなければいけない七五三。では、参加者のうち、誰が七五三の用意をするのでしょうか?それぞれ見ていきましょう!
着物は誰が用意するのか?
着物の用意は、地域によっても異なりますが、一般的には、
- 女の子の場合には、母方の祖父母
- 男の子の場合には、父方の祖父母
が用意します。
この習わしは、男の子は家を継ぐ事に由来して父方が用意し、女の子は将来嫁に嫁ぐ事から母方が用意すると言われていますよ。
ですが、最近では、着物の保管やクリーニング、購入費用の面から、着物をレンタルする方も多く、習わし自体が薄れつつあります。
また、祖父母世代の着物は、生地や縫製、仕立てなど質の良いものが多いです。ママ・パパの着物を自分の子供へ着せるなど、親子何代にも渡って、着物を大切に着ているケースもあります。
また、着物はお下がりで、帯や小物だけ、自分好みの気に入ったものを揃える、そんな方法もありますよ。
自分のお子さんに似合う着物を買って残したい!という方もいるでしょうし、写真スタジオにあるような今風の華やかな着物で写真を撮りたい!という方もいるでしょう。
- 着物は、男の子の場合は、父方の祖父母が用意
- 着物は、女の子の場合は、母方の祖父母が用意
- パパ・ママの着物を受け継ぐ
- 着物をレンタルする
- 両親が気に入った着物を買う
このように選択肢の多い着物の用意は、地域差や、その人の考え方に左右されます。 ご自分がどうしたいかを考えて、決められればいいですね。
食事は誰が用意するのか?
七五三は、「双方の祖父母をお招きしてお祝いした」という形になります。よって、基本的には、七五三の主催者は、子どもの両親。つまり、パパとママです。
最近は、七五三の食事会と言えば、外食する方が多いようです。ホテルや食事処などの予約や、料理のセレクトは、パパとママで行いましょう。
もしも、自宅で料理を振る舞う、または、ケータリングなどを頼む場合も、もちろん、両親が準備をします。
せっかくのお祝いの席なので、尾頭付きの鯛や赤飯、お刺身などいつもとは少し違った豪華な料理を用意してあげられるといいですね。
ちらし寿司や、てまり寿司などのお寿司も定番のお祝い料理として人気がありますよ。
七五三の料理は、料理にある程度決まりのある“お食い初め祝い”と違って、これといった決まりはありません。お子さんが好きなものを用意してあげてもいいですね。
七五三は誰が払う?

祖父母が集まるお祝いの席では、食事代を誰が払うか?で、もめるかもしれませんね。
七五三の主催者は子どもの両親なので、両親が食事代を持つことが多いです。あらかじめ「食事代はこちらで支払います」と伝えておくといいでしょう。
基本的には、子どもの両親が食事代を払いますが、お祝いの代わりに支払ってくれる人がいれば、そのご好意に甘えてもよいです。当日の支払いがスムーズに済むように、事前に打ち合わせておくことが大切です。
お祝いの席ですので、懐石や割烹のような豪華な料理を注文することも多いでしょう。人数が多ければ、その分、費用も高額になり、正直、支払いは大変なものです。
七五三では、祖父母からお祝い金をいただくことも多く、食事代をまかなえる程度のお祝いがあるかもしれませんね。そんな時は、ありがたく頂戴して、食事代を上手くまかなっていきましょう。
かわいい孫のためにお祝いをくれる祖父母には、感謝の気持ちを伝えるのを忘れないようにして下さいね。
まとめ

七五三にまつわる疑問を解消するべく、七五三は誰を呼ぶ?誰と行く?誰が用意する?誰が払う?に焦点をあてて、基本のマナーをまとめてみました。
七五三は、両親だけで行っても構いませんが、両家の祖父母に声をかけて、参拝や食事会に参加してもらうことが多いです。
七五三の用意をするのは、基本的には、祖父母でもなく、親戚でもなく、子ども両親です!参拝や食事会の予約はもちろん、食事メニューを決めたり、食事の支払いをするのも、両親になります。
祖父母からお祝い金をもらったり、支払いをしてくれる方がいるときは、ご好意に甘えましょう。そして、感謝の気持ちを伝えましょう。
着物は、男の子は父方の祖父母、女の子は母方の祖父母が用意するのが、習わしです。
しかし、最近は、その習わしも薄れてきています。着物をレンタルする方も多く、パパ・ママの着物を受け継ぐ方もいます。地域差やそれぞれの考え方に従っていいでしょう。
七五三は、大切なお子さんのお祝いだけに、人が集まれば、それぞれの意見があるものです。大変なこともありますが、ママが疲れない程度に、上手く調整していきましょう!
お子さんの成長を祈願する晴れやかな七五三を、家族皆が気持ちよく思い出として残せるといいですね。
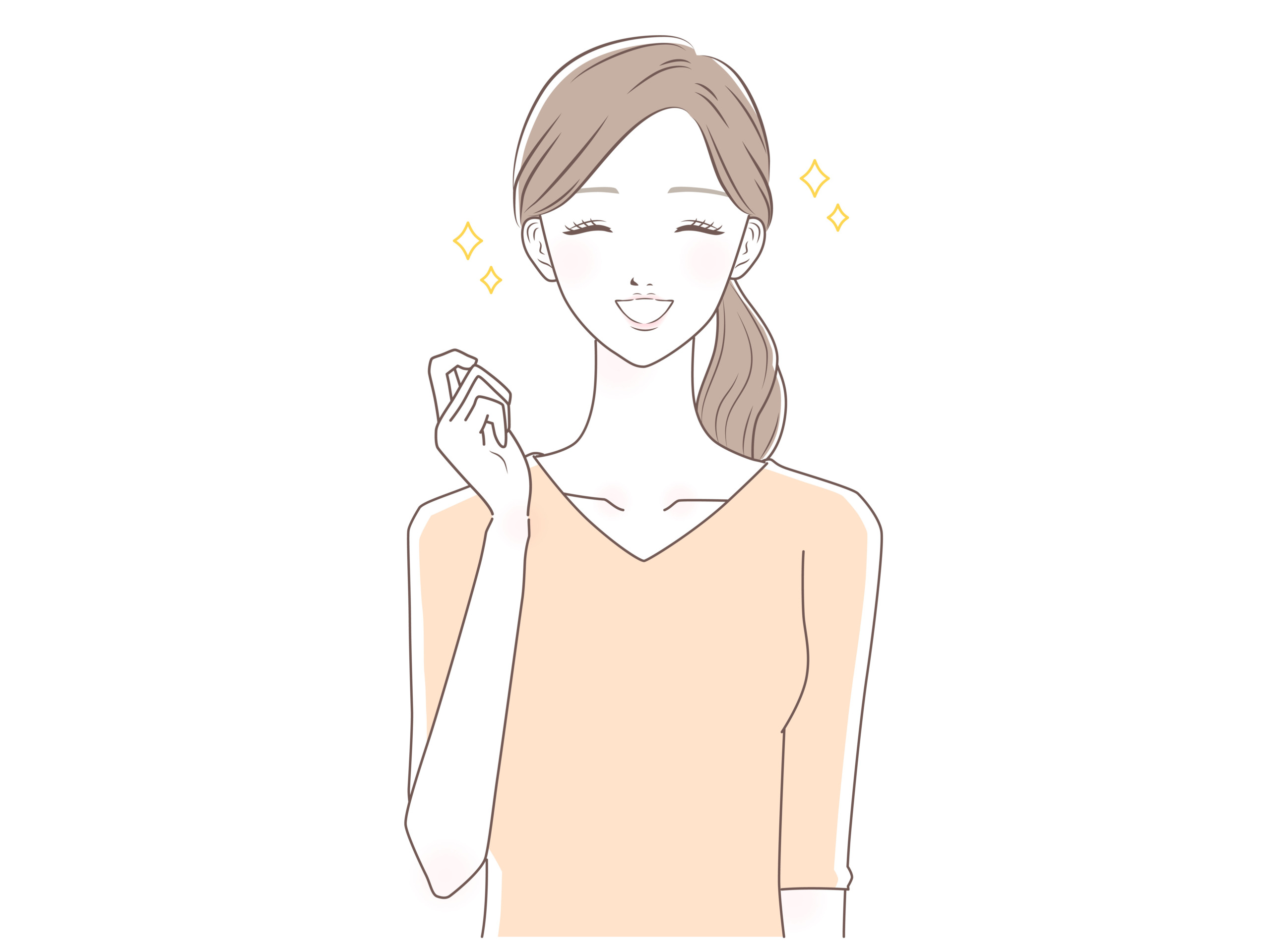
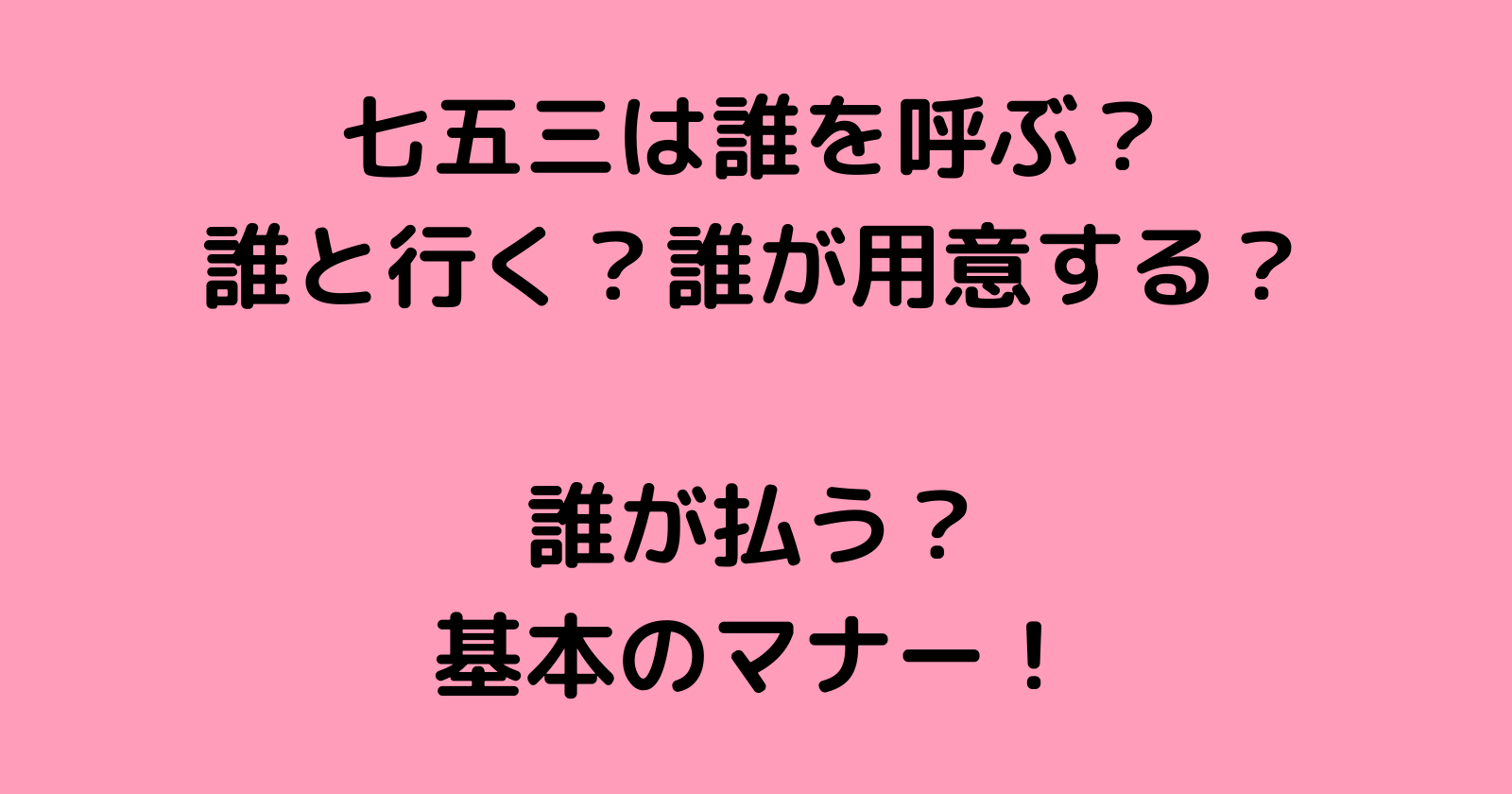
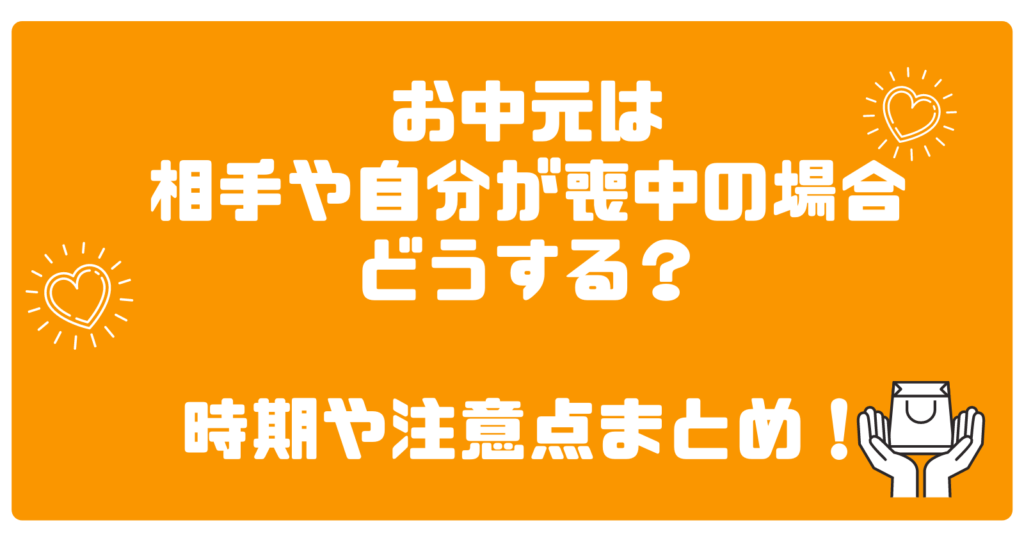
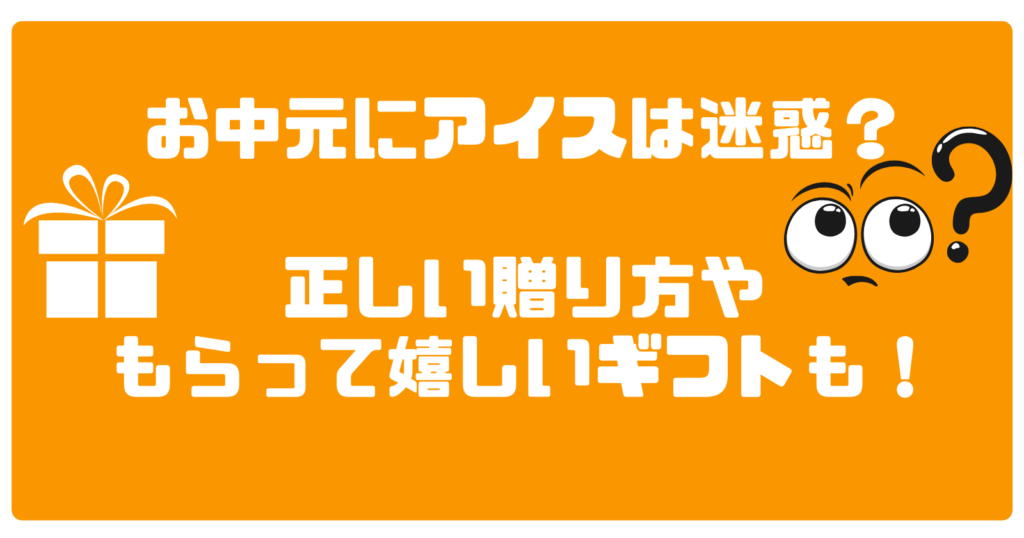
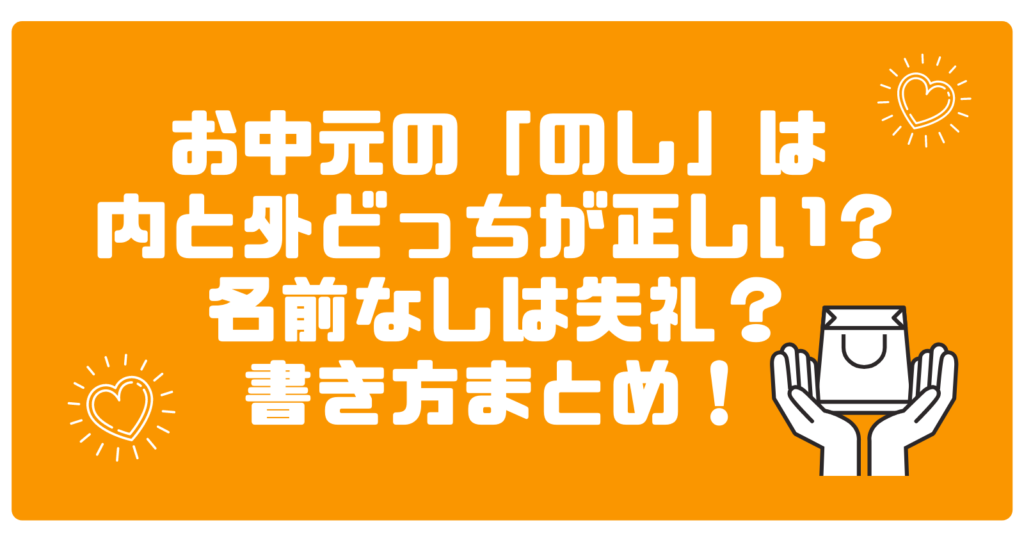
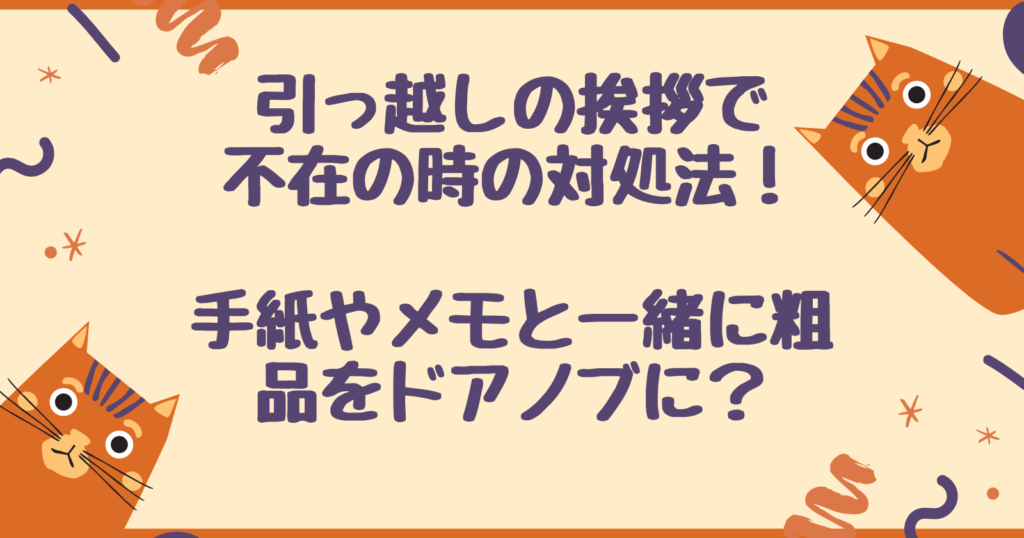
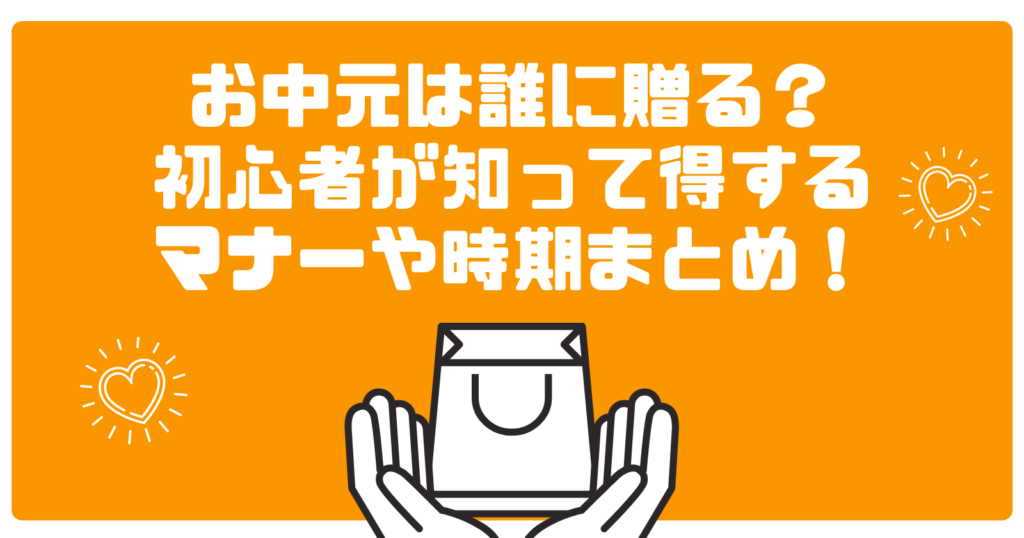

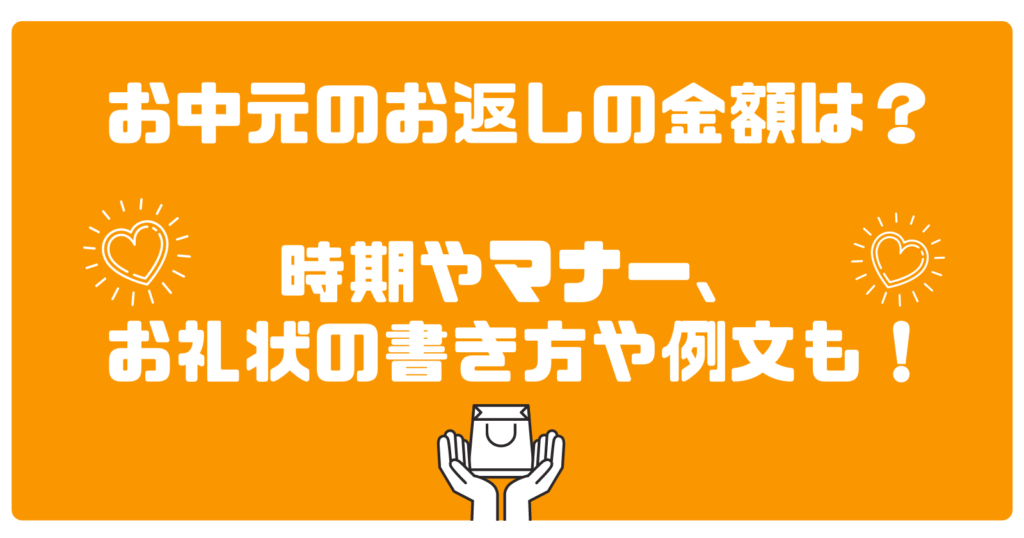

コメント